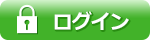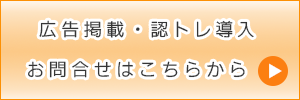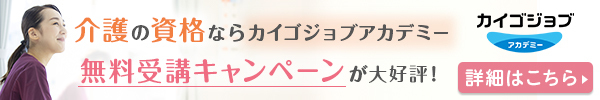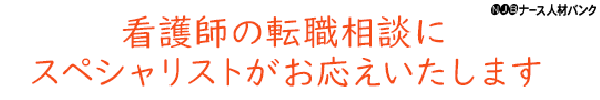日本が抱える認知症対策の課題 ~認知症の人を支える居宅介護の苦悩と孤立~
八巻 孝之(認知症サポート医, 宮城県仙台市)
【著者紹介】外科医、医学博士。東北大学第一外科(現総合外科)出身。肝臓研究班に所属、文部教官助手を経て仙台医療圏の科長部長職を歴任。2016年3月故郷の宮城県伊具郡丸森町国保丸森病院副院長に就任、2019年東日本台風による激甚災害を体験。2020年1月国立病院機構宮城病院に異動、「総合診療外科」部長職。医療と介護ケア、終末期医療、高齢者医療、災害医療等を執筆中。認知症サポート医、インフェクション・コントロール・ドクター(ICD)、スポーツドクター、東京2020メディカルスタッフ(MS)等。
はじめに
日本は、「共生」を目指し、「認知症バリアフリー」の取組を進め、「共生」の基盤下に「通いの場」の拡大などの「予防」へ取組んできた。しかし、居宅介護を支える家族の身体的・精神的・経済的な負担は増える一方である。介護保険制度スタートから20年が経過し、認知症と介護をめぐる状況はこの10年間で大きく様変わりした。高齢者のみの世帯の増加は著しく、介護家族は「老老介護」や「シングル介護」がさらに増え、「嫁介護」はますます減っている。本稿では、認知症の人を支える家族のと孤立に焦点を当て、日本が抱える認知症政策の課題について述べる。
Ⅰ. 事例紹介~居宅介護の光と影
1)島崎由美子さんのケア
紹介する事例は、認知症サポート医である筆者が宮城県伊具郡丸森町で出会った、アルツハイマー型認知症を10年間患う88歳の男性を支える娘、島崎由美子さん(薬剤師, フリーランスライター)の居宅介護の日常である。この認知症の人は、2020年5月26日に掲載いただいた筆者のコラム「関係性の中で変化する自己決定の意味~認知症の人への家族介護の日常から~」で紹介した。2年後の現在も認知症ねっと、編集部ピックアップで紹介いただいており、関係者の方々に深く感謝を伝えたい。
欧米生活が長い由美子さんは、2年半前の新型コロナウィルス感染症のパンデミックのため、オランダから一時帰国した。取材にあたって、彼女が日本で初めてユマニチュード1)を学んだ当時の写真を見せてくれた(写真1)。掲載写真ならびに個人情報の公開については、本人の意思を推定できる彼女の同意を頂いた。
彼女は、認知症の人に対するケアについて、「見るということは、実際にはとても難しいことです。ただなんとなく相手の顔を見るのと、相手の視野に入って相手からも見てもらい、アイコンタクトを得るのとは違いますし、腕を取るにしても触れるとつかむは違います。」と語った。要するに、われわれが行うケアの全ての動きには相手に対する言語的・非言語的なメッセージが含まれているのですが、これらの行為を意識的に正しく実践している場面が実はとても少ないらしい。彼女に、実際の居宅介護を見せて頂いた。彼女の認知症の人と関わるスキルはまるで魔法のようだと言いたくなる。彼女は、見る・話す・触れる・立つ、の4つのスキルはどれもケアだけに特別なものではないという。そして、日本の看護や介護の懸命な姿、そこにあるポテンシャルは大きいと感じているという。ヨーロッパと日本では文化も習慣も大きく違うが、自分が大切に思う人に対しては自然に行うこうしたコミュニケーションを高齢者に対してはなかなか使えないでいると評した。

写真1 右は島崎由美子さん、左はフランスのジネスト・マレスコッティ研究所創設者で所長を務めるイヴ・ジネスト特任教授(2013年当時, 東京)
2)起床・排泄・着衣の場面(写真2)
「ケアの場面で私たちは、ドアをノックすることはあっても相手の反応を待たずに布団をはがし、入室した数秒後にはおむつに手をかけてしまっていることはないでしょうか。これでは、コミュニケーションにおける出会いの準備とケアの準備をいっきに飛ばして、いきなりケア行為に入ってしまっています。職務行為であれば当たり前だと思われるかもしれませんが、私も初めはその意味が分かりませんでした」。しかし、明らかに相手の反応が変わるという経験を重ねるに由美子さん自身の考えも変わっていったそうである。ケアを行う人がどんなに優しい気持ちを持っていたとしても、その気持ちを相手が理解できるイメージで表現しなければ相手には決して届かない。その気持ちが相手に伝われば、たとえ認知機能が低下した人であっても、安心し、やがてケアを受け入れてくれるようになると、詳しく説明してくれた。彼女は、一つのケアの後に「きれいになって気持ちよかったですね」と父に語りかけており、認知症の人からポジティブな感情を引き出しながら次のケアへ繋げている。

写真2 コミュニケーションにおける出会いの準備とケアの準備、そしてケア行為を始めた島崎由美子さん。着衣・排泄ケアへと身体的負担が続く。
3)食事の場面(写真3)
普段何も反応がない、何も理解しないとされる重度認知症の父に対して、由美子さんは息づかいを感じられるほどの絶妙な距離で語りかけながら相手の視線を捉える。まるで実況中継をするように絶えず話しかける。すると驚くことに、わずかな時間で相手に反応と発語が見られた。「食事は、他者が自由で素敵に過ごす大切な時間、おせっかいをしないこと」と語った。

写真3 右が認知症の父、左が父の前で常に笑顔を絶やさない由美子さん。
4)支える家族の苦悩
特に印象的なことは、「あなたは大切な存在」であると安心感やポジティブな気持ちを言葉やしぐさでしっかり伝えていることである。アイコンタクトが成立したら2秒以内に話しかけながら相手に触れるなど、そのスキルはとても具体的で分かりやすい。由美子さんは、「ケアをする人にもよい変化が生まれる」と語り、続けて「私の日本のケアに対する印象は、決して父であっても他者であり、その人の自由意思である嫌がるという反応は、ケアを受ける人の選択としてではなくケアを与える人への対抗や拒否と受け止められやすいということ。これからの日本、一番大きな課題は、ケアを与える人のバーンアウトではないでしょうか。相手にケアを拒否されたり叫ばれたりしても、それは双方向のコミュニケーションが十分ではなかったのであって、ケアをする人の人間性を決して否定されたのではないのです。日本は、その視点を持ち続けなくてはいけません。私の2年半の居宅介護にはたくさんの経験があります。何よりも、ケアがスムーズにいくようになるとうれしいですよ。支える人の心にケアの満足感が生まれるのですから」と笑顔で語った。故郷の里山で彼女が経験した居宅介護の苦悩と孤立とは、かかりつけ病院の入院しぶりや退院勧告、入所希望先の特別養護老人ホームからの拒否など、著者にも到底受け入れ難い事由である。
5)ケアへの希望
由美子さんのスキルは、日本のケアの在り様を否定するものではない。現在のケアと組み合わせて取り入れることができるものである。彼女が最後に語った、「高齢化がさらに進み、さらに増える認知症の人に対するケアが模索されている中、日本の医療・看護・介護に携わる、いわゆる与える側の人は、他者との関わりを持つ世界で最も素晴らしく輝くはずです」という一言は、様々な困難に直面している高齢者、特に認知症の人のケアに対し、希望を与えるだけでなく、ケアする人のバーンアウトを防ぐなど、ケアを受ける人、与える人の双方に明らかな変化をもたらすのではないかと思われる。
Ⅱ. 日本が抱える居宅介護問題
日本では、認知症の人が2025年までに700万人に増加すると推計されている。厚生労働省が取りまとめた2019年度国民生活基礎調査の概要2)によると、高齢者の介護は、現在でも家族によるものが68%(同居54%、別居14%)を占めている。2018年度の介護保険の要介護認定者は669万人で、介護の必要となった原因の1位が認知症である。介護離職も年間10万人に上り、深刻な問題といえよう。多くの高齢家族が認知症の人を抱え込む傾向にあると言える。
2015年に策定された国家戦略「新オレンジプラン」には、地域での見守り体制の整備や介護者の負担軽減、政策の立案・評価に認知症の人や家族が参加することなども盛り込まれている。ほとんどの人は住み慣れた地域でケアを受けたいと願っている。一方、認知症の人に対する国民の理解が深まっている現在の日本は、医療費窓口負担増や介護の給付抑制と利用料の引き上げ、年金削減等、高齢者の生活に負担増を強いている。
公益社団法人認知症の人と家族の会は、2019年9月~2020年1月に認知症に関する4つのアンケート調査を行い、認知症に関する意識について、本人、家族、一般市民、支援者の、4つの角度から調査・分析している3)。この度、調査報告書が公開され、介護家族の現状と苦悩について、新たな示唆を得た。20年前の調査で33%であった息子の配偶者、いわゆる嫁による介護は、9%に減少し、実の子が31%から44%に増えた。65歳未満の介護者のうち、67%が仕事をしながら介護をしていた。認知症の人の他に要介護状態にいる家族は11%に及んだ。さらに、体調不良を訴える介護家族の割合が増えた。1疾患の人が42%、2疾患が19%、3疾患が11%、合計72%の人が治療中であった介護する人は、自分が倒れた時の不安を常に抱えているようである。また、昼夜を問わず、一日中介護をしている人が25%もいて、多くの人が睡眠不足や肩こりなどを訴えていた。
10数年前から認知症に対する国家戦略が実行に移され西武が進む中、認知症に取り組む当事者として、これまで以上に介護家族を孤立させてはいけない。また、相談窓口の多様化による幅広い支援が望まれる。著者が勤務する医療施設もそうなのだが、特に、認知症疾患医療センターは、専門医療と生活支援を兼ね備えた場として、地域のかかりつけ医と連携しながら、認知症の人と家族の思いや暮らしがより良いものになるという期待感に応えるべき医療機関ではないだろうか。
認知症の人の行動・心理症状(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia: BPSD)は、認知症の人が何らかの要因によって脅かされた結果として出現し、介護者にとっても大きなストレスとなり、しばしば介護破綻にも直結する。一方、認知症の人にBPSDが起こった文脈を理解し安全が感じられる環境を作り出すことは、同じ地域に暮らす人々の安心を確保することにも繋がりり得る。オーストラリアDBMASの多職種専門家によるタイムリーな助言・介入サービスは、日本において自宅や施設での認知症の人の暮らし、そして介護家族の暮らしに大きな助けとなるのではないかと思われる。オーストラリアでは、各州がDBMASの形を変えて実情に合わせつつBPSDに対するマネジメント機能を発揮している。日本においても、機能的な支援として期待したい。
認知症の症状が進行すると、訪問介護やデイサービスといった自宅にいながら受けられる居宅サービス利用の継続が困難となる。その時に頼りになるのが介護施設である。著者は、認知症が進行した状態を理由に施設から入居の拒否を通告された経験をもつ家族に時々遭遇する。介護施設には複数の種類があり、認知症の人が入居可能な施設がその中にいくつかある。例えば、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)、高齢者向け住居に分類される有料老人ホーム、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、サービス付き高齢者向け住宅などがそうである。ただし、各施設でサービス内容や入居対象者には差があるだけではなく、認知症の方にも対応できる職員数などの体制を整えることが困難な施設も少なくない。さらに、どのくらい手厚い介護が受けられるのか、対応できる医療的ケアの種類などにもかなりの幅がある。受け入れ先が満床で常に不足している。認知症の人の介護抵抗や拒否は入所不可能な理由になり易い。このように、認知症の人と介護する家族が安心で安全なより良い暮らしを送るためには、環境と周りの関係者の対応が極めて重要である。
おわりに
居宅介護を支える家族が置かれた状況は、これまでも、現在も、これからも、様相を変えながら困難な状況で推移していくだろう。認知症の人を居宅介護で支える家族の暮らしを直接的に支援できる社会に成らなければ、日本の認知症施策が成功したとは言い難い。今後どのような取組が必要か、改めて考え具現化いていく必要がある。島崎由美子さんのように認知症の人を支える居宅介護の希望の灯を消し去ってはいけない。
著者の利益相反:本論文発表内容に関連して申告なし。
引用文献
1) 日本ユマニチュード学会ホームページ. ユマニチュードとは. https://jhuma.org/humanitude/(2022年5月5日閲覧)
2) 厚生労働省. 2019年国民生活基礎調査の概要. https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa19/index.html (2022年5月6日閲覧)
3) 公益社団法人 認知症の人と家族の会. 認知症の人と家族の思いと介護状況および市民の認知症に関する意識の実態調査. https://alzheimer.or.jp/wp-content/uploads/2020/04/rouken2019.pdf (2022年5月6日閲覧)
(筆者メールアドレス:yamaki821@nifty.com)
- 認知症は予防できます!! –認知症「予防」のための3資格-
- 認知症予防医/広川慶裕医師の新刊「脳のスペックを最大化する食事」7/20発売
- 認知症予防医/広川慶裕医師の新刊「潜伏期間は20年。今なら間に合う 認知症は自分で防げる!」
- 広川慶裕医師の、認知症予防のことがよく分かる『認トレ®️ベーシック講座』開講!
- 知ると知らないじゃ大違い!民間介護保険って何?
- 酸化ストレスを減らすと認知症予防に!秘密はサプリメント
- ユッキー先生の認知症コラム第92回:あるべき姿の認知症ケア
- 認知症専門医による認知症疾患啓発イベントを開催
- ポイントは食生活にあった。認知機能維持に必要なのは・・・
- 認知症予防は40代から!摂ると差が出る栄養素とは。
- 山口先生のコラム「やさしい家族信託」第17回:Q&A 外出自粛で、認知機能の低下が心配。家族信託、遺言、後見、今できることが知りたい
- 【広川先生監修】5分で分かる認知機能チェック(無料)はこちら
- 認知症は予防できるの?
- 認知症の種類とその詳細はこちら