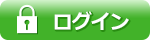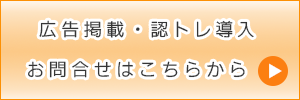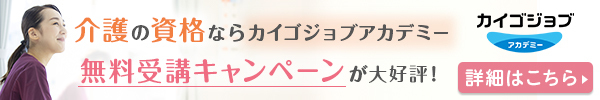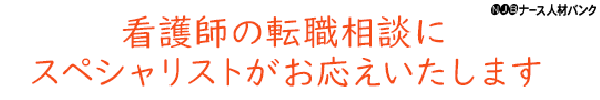関係性の中で変化する自己決定の意味~認知症の人への家族介護の日常から~
八巻 孝之(認知症サポート医, 宮城県仙台市)
【著者紹介】外科医、医学博士。東北大学第一外科(現総合外科)出身。肝臓研究班に所属、文部教官助手を経て仙台医療圏の科長部長職を歴任。2016年3月故郷の宮城県伊具郡丸森町国保丸森病院副院長に就任、2019年東日本台風による激甚災害を体験。2020年1月国立病院機構宮城病院に異動、「総合診療外科」部長職。医療と介護ケア、終末期医療、高齢者医療、災害医療等を執筆中。認知症サポート医、インフェクション・コントロール・ドクター(ICD)、スポーツドクター、東京2020メディカルスタッフ(MS)等。
伊達政宗初陣の地、金山要害と呼ばれた宮城県伊具郡南部の丸森町金山。そこにひっそりと城跡が佇む。郷土の戦国史を調べたくてこの地を訪ねた私は、本丸跡から十五分程降り立った麓で、見応えのある土塀の門構えと左右に扉が開く格調高い開き門に出くわし、思わず立ち尽くしてしまった。金山の城主は、仙台藩伊達氏の家臣、初代中島宗求である。私の眼前に建つ武家屋敷は、中島家の筆頭家臣、島崎家の屋敷であった。開き門に並ぶ通用口の扉が突如開いて、私と年頃の同じ細見の女性が現れた。この日は「寒の戻り」にもかかわらず、鮮やかなオレンジ色のTシャツと青空色の半ズボンであったこの女性は、両手に大きなゴミ袋を持ちながら「何か御用っすか」と私に問いかけてきた。咄嗟の行動が見当つかずに私は思わず、「あの、ゴミ袋、一つ持ちましょうか」と応えた。ゴミ置き場からの帰り道、彼女は私に「由美子」と名乗った。オランダのデン・ハーグに住むフリーライターだと言う。新型コロナの世界的流行で一時帰国せざるを得ず、ここは彼女の実家だった。彼女はここで、母親と共に重度認知症の父を介護しているのだ。半開きの通用口の向こう側に、千坪の日本庭園と母屋、使用人が住んだだろう平長屋、蔵などが建ち並び、厠と井戸が一つずつ見えた。彼女は、物欲しそうに覗く私の知的好奇心を察してか、咄嗟に私を敷地内に招いてくれた。
家主は、七年前に発症したアルツハイマー型認知症の高齢男性である。認知症サポート医である私の身勝手な評価によれば、認知症テストで知られる長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)とミニメンタルステート検査(MMSE)の結果は、おそらく三十点満点の零点であるに違いない。元々、西洋の文物と若い異国女性を好む高校英語教師だった。彼の傍らで介護する高齢の妻もまた元家庭科教師だと聞いた。オランダ色に輝く目前の娘は、十三代目の一女で、六言語を話す元薬剤師、現在はフリーライターである。オランダでの彼女は、尊厳死の意思を表示する多発性硬化症(難病)の女性を介護した経験を持つ。彼女が帰国後に書いた、「ニッポンが抱える不登校問題へのメッセージ」を、日本教育新聞社WEB版で私に紹介した時、その文面は西洋人として生きる彼女の「自由、平等、寛容、博愛」の言葉で溢れていた。偶然の出会い、彼女が語りかけた難病、安楽死、認知症の話題に、医師である私は強く引き寄せられてしまった。
数週間後のある日、娘は私を屋敷に招き、家族を紹介してくれた。家主はリビングテーブルに座る私の向こう側に居て、立ちと座りを繰り返し何となくよそよそしかった。日中の彼は、ワイシャツとズボンで過ごすハイカラスタイルのイケ面で、食事中は自分の右手を大好きなギター譜に伸ばし、その表紙の見事に綺麗な異国女性の頬を撫で、ゆっくり頁をめくると、イディッシュ(中東欧ユダヤ)の牧場から市場へ売られる哀れな子牛の歌、ドナドの所で必ず自身の手を止める。ワイシャツのボタンは自分でずらさずに留め、引き抜いた一枚のティッシュはまるでハンカチのように丁寧に小さく畳み、そっと左胸のポケットに収める。目前のご馳走は必ず時間をかけて一種類だけを食する。時には箸先でランチョンマットに零れた食物を捉える。私が話しかければ、辻褄が合ったとたん、突如零れるような笑顔を見せてくれる。噛み合わないと横目に、「あれ、あれ」と千坪の庭園を指差して上手に私をはぐらかす。娘の腹の奥から発する声はとてもストレートで愛情豊かだ。寄り添う妻の発する言葉は、自身の身勝手な想いに包まれていた。私に向かって、「生きているだけでいいよ」と娘が言い、「自分が困る、とても大変」と妻が愚っぽく話す。ある朝、日課のデイサービスに出かける前、家主の入れ歯を綺麗に磨きたい妻は、相手の口を開かせようと自分の両手を伸ばすが、見事に抵抗されて30分以上が過ぎ、やってきた娘が「歯をみがこう、歯をみがこう」を大声で歌い出した時に、抵抗する相手が一緒に歌い抱いた光景には度肝を抜かれた。私は、目の前の筍ご飯に舌鼓を打ちながら、三人の関係性の中に認知症の人の尊厳とは何かに想いを馳せていた。
他者との関係性に見え隠れする家主の意思と価値の変容はとても多彩だった。娘の、腹の底から絞り出す力強い声は、なぜか父の胸中に響き、他者にとって決して耳障りな声ではなかった。認知症の人はとてもストレートで愛情豊かだ。それを知る娘は、「生きているだけでいいのよ、PAPA!」と言い放った。私が滞在した限り、寄り添う妻の発する言葉は自分中心の身勝手な想いに包まれていた。事ある度に「自分が困る、とっても大変」と愚痴った。日課のデイサービスに出かける前、家主の入れ歯を綺麗に磨きたい妻は、彼の口を何とか開かせようと自分の両指先を口元に伸ばしたが、彼の見事な抵抗を受けて三十分以上の時があっという間に過ぎた。あきらめかけた妻の前で娘が「歯をみがこう、歯をみがこう」と身振り手振りで歌い出し、家主が急に笑顔で口を大きく開けながら歌い出す始末に、私は一瞬にして度肝を抜かれた。
今、新型コロナウイルスの感染拡大が介護福祉分野にも連鎖的な影を落とす中、自分自身は決して感じたことのない他人の感情の心中へ自己を投入する能力を、これほど要求される仕事はほかに存在しないのではないだろうかと思う。相手の立場に立つことは支援する者として大変重要な能力であるが、相手は自分と異なる人生を歩んでいる他者であることを忘れてはならないという考えに辿り着いた。介護を実践するということは、基本的に「わからない」という身の置き方に定位する活動でなければならないと強く感じた。いつも当事者である相手の思いを感じて、相手を推し量り、確かめながら事を進める必要がある。特に言語的なコミュニケーションが図りにくい認知症の人のケアにおいては、相手の真意に近づくための道筋は、その人との関わりの積み重ねの中に尊厳として描かれていくのだと思う。
自分の真の意思を適切に表現して自己決定をゆるぎなくすることが困難なのは、決して認知症の人だけではない。私は医師として、例えば、誤嚥性肺炎で入院していたある高齢者は退院期限が迫り、腹に穴を開けて胃瘻を造設して入院期間を延長するか、可能な限り口から食べる訓練をして誤嚥性肺炎のリスクと向き合い自宅へ戻るか、近隣の介護施設へ移るかの選択を示された時にも、「自分の思いはあるが、言えば家族に迷惑をかけるので言わない、皆に任せる」と語った患者に出合った事がある。周囲の思いを汲み、遠慮しながら人生の最期を過ごす高齢者、その家族もまた決定したことにゆるぎながら別れの時を迎え、その後も 「あれでよかったのか」と自問自答を繰り返す様子を何度か診てきた。先に紹介した島崎家の居間の柱には自由、平等、博愛と書かれたメモ紙が張られていたが、まさしく、日常のその人らしい物事の決定は、介護する側の取り巻く環境や人間関係、身体状況、精神状態、決定による影響などにより常に相対的に選択され、変化しているように思う。認知症の人の意思表示は概ねストレートであるが家族の関わりにより変化し、認知症の人は、特に不安なこと、嫌なこと、いつもと違うことには敏感に強く反応して自身を守ろうとするようだ。安心できること、嬉しいこと、役割を果たすことには満面の笑顔がみられる。言葉で適切に表現できないことが自己決定できないことにはならない。自己決定できないと決めつけて、認知症の人の意思を無視すれば、それは大きなおせっかいとなる。
認知症の人の問いかけに介護や福祉、看護、倫理など、各領域の学識はどう応えることができるのか。「わからない他者」と向き合い、自己決定の意味を深いレベルで推し量りながら、生いていることを支援し、必要な時に医療とつなぐシームレスケアの実践が求められていると思えてならない。老いは花、君(=娘)は美し。私は、偶然に遭遇した島崎家の日常に、ゆるぎない自己決定の尊厳、本来求められている理想を垣間見た気がする。
(筆者メールアドレス:yamaki821@nifty.com)
- 認知症は予防できます!! –認知症「予防」のための3資格-
- 認知症予防医/広川慶裕医師の新刊「脳のスペックを最大化する食事」7/20発売
- 認知症予防医/広川慶裕医師の新刊「潜伏期間は20年。今なら間に合う 認知症は自分で防げる!」
- 広川慶裕医師の、認知症予防のことがよく分かる『認トレ®️ベーシック講座』開講!
- 知ると知らないじゃ大違い!民間介護保険って何?
- 酸化ストレスを減らすと認知症予防に!秘密はサプリメント
- ユッキー先生の認知症コラム第92回:あるべき姿の認知症ケア
- 認知症専門医による認知症疾患啓発イベントを開催
- ポイントは食生活にあった。認知機能維持に必要なのは・・・
- 認知症予防は40代から!摂ると差が出る栄養素とは。
- 山口先生のコラム「やさしい家族信託」第17回:Q&A 外出自粛で、認知機能の低下が心配。家族信託、遺言、後見、今できることが知りたい
- 【広川先生監修】5分で分かる認知機能チェック(無料)はこちら
- 認知症は予防できるの?
- 認知症の種類とその詳細はこちら