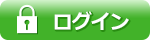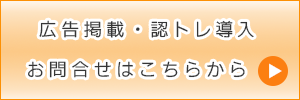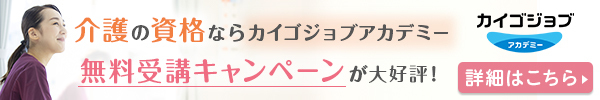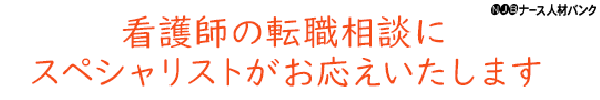認知症とどう向き合うか:患者さんの場合、家族の場合~松本一生先生インタビュー
松本診療所ものわすれクリニック 院長 松本一生先生インタビュー

認知症専門クリニック「松本診療所ものわすれクリニック」の院長である松本一生先生は、25年にわたり認知症の患者さんとかかわってきました。その数はおよそ4000人にも上ります。そんな松本先生に、多くの患者さんと家族を支えてきた経験からみえてきた「認知症との向き合い方」について、お話しいただきました。
- 話し手
-
 松本診療所ものわすれクリニック理事長・院長松本一生先生
松本診療所ものわすれクリニック理事長・院長松本一生先生
患者さんと家族では認知症との向き合い方に違いがある
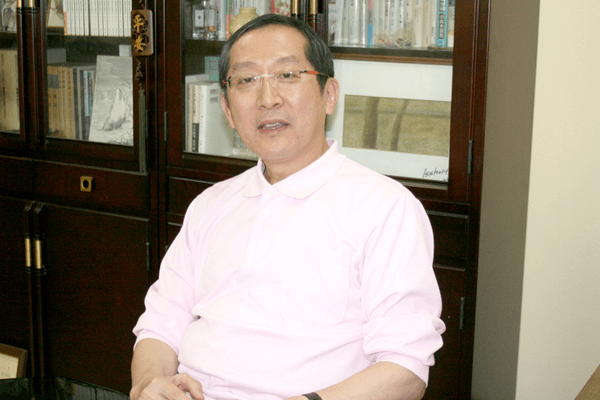
──認知症と向き合うには、まず「告知」ということが1つの課題になってくると思われますが。
私の場合、まずは言葉や素振りなどから患者さんの気持ちをくみ取るようにしています。そして、診察開始から早い段階で「診断がついたら病名の告知を希望しますか」と、本人もしくは家族に伺うようにしています。これまでの経験から、自分のことだからきちんと知りたい、今後のことを考えるためにつらいことでも聞きたいという方には、告知したほうがその後の病気の進行が抑えられると感じています。
一方、患者さんの意向を置き去りにして、家族主導で告知が行われた場合、結果を知った本人は絶望の中に沈んでしまい、病状が早く悪化することが少なくありません。患者さんのこれからを考えるとき、医者としては、患者さんや家族がどのような思いで病気と向き合おうとしているかということを見抜くことが重要なポイントになっています。
──認知症がわかったとき、人にはどのような心の動きが現れるのでしょうか。
精神分析学者・フロイトによる「対象喪失」の概念があてはまると思います。対象喪失は、大切な人や物、慣れ親しんだ環境、身体の一部、夢や目標など、自分にとってかけがえのないものを失うことで、その心は時間とともに「驚愕→否認→怒り→抑うつ→適応→再起」という経過で整理されていくとされています。
──そのような心の動きを背景に、患者さんや家族は認知症にどのように向き合っているのですか。
認知症は、現在のところよくなることはなく、進行する病気です。そのため向き合うことに対する恐怖やつらさは強くなりますが、心の整理は通常どおりに行われます。ただその向き合い方となると、患者さんと家族では違いがあります。患者さんの場合、認知機能が低下していく中で、自分のこととして向き合っていくため、対象喪失の体験は少なくて済むことが多いのです。それに対して、家族は、患者さんの変化のたびに対象喪失のプロセスを繰り返すことになります。ですから、サポートする立場としては、患者さんはもとより、家族へのケアも重要になると考えています。
「認知症はなったら終わり」ではない
──患者さんが認知症と向き合う場合、どのように考えればよいでしょう。
「認知症になった。それでは自分はどう生きていこう」というように、これから違った人生が始まるということを、まず認識してほしいと思います。認知症がわかると、物を忘れたり、何かができなくなったり、生活が不自由になることばかりに目を向けてしまいがちですが、それとどう付き合っていくか考えることが大切です。
例えば、慢性の関節痛があったら、なるべく痛みを感じなくてすむよう、生活様式や活動の仕方などを工夫しますよね。それと同じように考えてもらえたらいいかなと思います。私たちの身体は、年齢とともに老化します。認知症も身体の老化と同じ線上にあるのです。それを踏まえたうえで、いかによい状態を保つかということが重要になってきます。
──よい状態を保つということはどういうことですか。
「認知症になったら終わり」などと言う人もいますが、決してそうではありません。かつて、がんもそう言われましたが、今ではうまくつき合いながら生きていくという考え方になりました。認知症も同じです。少しずつ不自由や不都合が増えたとしても、変わらずに生活できる部分は少なくありません。うまくつき合っていけば、よい状態を維持したまま生活していくことは可能なのです。
私の患者さんで、70歳で告知して、95歳になる今も大きく変わることなく受診を続け、自宅で生活されている方がいます。その方は、認知症になったことで、自分が得てきた知識や財産を次世代に引き継ぐ役目に気づいたとおっしゃり、着々と行動に移されています。それが、生きがいになっているのかもしれません。自分はまだちゃんとやっていけると思うことが重要だといえるでしょう。
──具体的に行うべきポイントはありますか。
よい状態を保つために、患者さんは決して1人にならないでほしいのです。家族以外にも、医者や看護師、介護士、作業療法士など、何かあったときに相談できる相手をもつようにすることです。それが安心につながり、心を安定させます。何よりも大切なことです。
介護家族はもう1人の当事者である

──介護家族が認知症と向き合うとき、どのようことに気をつけたらよいのですか。
認知症において、介護する家族はもう1人の当事者です。ですから、家族も1人にならないことが大切になります。1人で抱え込んで頑張ってしまったり、ほかの人を入り込ませないようにする家族に出会うことは少なくありません。そうではなく、人の手を借りる、社会の助けを得ることを厭わないという考え方をもつようにしてほしいと思います。それが、物理的に助けられるだけでなく、自分には相談する人がいる、助けてくれる人がいるという、心の支えになり、余裕にもつながります。
仮に認知症を患った家族が夜中に混乱したとき、介護する側が「明日相談できるから大丈夫」と思えるかどうかは、患者さん本人の気持ちにも影響します。自分の行動に対し、家族から不安な表情や困った表情がフィードバックされると、患者さんの混乱はより強くなります。しかし「大丈夫」と余裕の気持ちが現れた表情なら、本人は徐々に落ち着いていきます。家族の表情や態度は非言語的なメッセージなのです。
──家族も安定した気持ちで患者さんとかかわることがよいのですね。そのために何か気をつけたいことはありますか。
家族が安定した心理を保つためには、患者さんが現在どのような状態にあるのか診断をきちん受け、経過とともに評価してもらうことが大切になります。
当院の場合は、中核症状の程度とBPSDの程度を合わせて図式化し、本人の状態が現在どの位置にあるか目でみてわかるようにしてお伝えしています。そうすると、家族も状況を把握しやすくなります。その時々の患者さん状況を適切に把握し理解することは、一緒に生活するための欠かせない要素です。
──きちんと介護したいという思いから、介護家族が無理をしがちになることもあると思うのですが。
介護家族が追いつめられていることを示す3つのポイントがあります。
1つめは、「介護はつらくない」と言いつつも、何らかの身体症状が現れている状態。身体は正直です。肩が痛い、頭が重い、ふらつくなどの不定愁訴の原因は、介護によるストレスにほかなりません。
2つめは、「私のこれからの人生は介護に捧げる」という考え。これは自己犠牲を自らに強いることで、破綻を招きかねません。自分の生活を7、介護を3ぐらいの割合で考えていくことが、介護を続けていくための秘訣であることを頭に置くことが大切です。
最後は、「だれの手も借りなくても大丈夫」という孤立した介護。すでに話しましたが、抱え込むことが自らを追いつめてしまいます。
これらは客観的な目安であるとともに、家族自身の振り返りにもつながります。気づかないうちに、このような考えに陥っていないか、チェックすることが大切です。
──それでも行き詰まってしまったとき、何か方法はありますか。
在宅での介護が無理なら、施設入所も1つの選択肢です。きちんと介護を行うということは、必ずしも自宅で介護するということではありません。家族が心理的に落ち着かないまま介護を続けるよりも、むしろ入所したほうが本人の安定につながるケースも多いのです。
家族以外の視線、より多くの人のまなざしがあったほうがよい状態に結びつく人もいます。水入らずで介護することが、患者さんの最上の幸せであるという価値観は捨てたほうよいと思います。
施設に入所させることを介護の手抜きなどと考えずに、患者さんの介護にあてる割合を少し減らして、1つの家庭として、家族自身の人生として、自分たちの生活を立て直すことも大切です。その中で、施設と連携して、介護を行っていくことは可能なのです。
- 認知症は予防できます!! –認知症「予防」のための3資格-
- 認知症予防医/広川慶裕医師の新刊「脳のスペックを最大化する食事」7/20発売
- 認知症予防医/広川慶裕医師の新刊「潜伏期間は20年。今なら間に合う 認知症は自分で防げる!」
- 広川慶裕医師の、認知症予防のことがよく分かる『認トレ®️ベーシック講座』開講!
- 知ると知らないじゃ大違い!民間介護保険って何?
- 酸化ストレスを減らすと認知症予防に!秘密はサプリメント
- ユッキー先生の認知症コラム第92回:あるべき姿の認知症ケア
- 認知症専門医による認知症疾患啓発イベントを開催
- ポイントは食生活にあった。認知機能維持に必要なのは・・・
- 認知症予防は40代から!摂ると差が出る栄養素とは。
- 山口先生のコラム「やさしい家族信託」第17回:Q&A 外出自粛で、認知機能の低下が心配。家族信託、遺言、後見、今できることが知りたい
- 【広川先生監修】5分で分かる認知機能チェック(無料)はこちら
- 認知症は予防できるの?
- 認知症の種類とその詳細はこちら