行方不明となった認知症患者のうち5日以降の発見で生存率0に
2016年6月10日
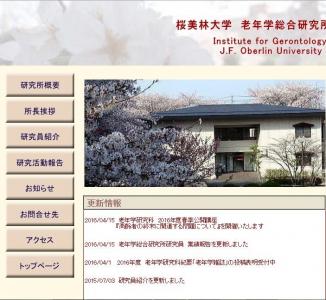
行方不明発見の遅れが存命率低下に繋がる
平成28年5月26日、認知症から由来する徘徊によって行方不明となってしまったもののうち、発見までの時間経過により生存率が低下してしまうことが、桜美林大学老年学総合研究所鈴木隆雄所長らの研究により判明したと報じられた。
776人の家族を対象に調査
今回行われた調査は、厚生労働省からの研究費によって桜美林大学老年学総合研究所鈴木隆雄所長らが行った。
そして、行方不明届が提出された認知症の疑いがある者の中から、死亡事例を含む776人の家族を対象に調査票でもって行われたのである。
生存率が翌日発見で約6割5日目では0に
これらのうち、204人から回答がありそれらを分析した結果、発見までの日数が5日を超えてしまった場合において、生存者がいなかったことが判明した。その一方で、当日中の発見では約8割翌日で約6割そして3日から4日で約2割の確率で、生存しているという事実も明らかとなっている。
また、死亡事例となってしまったもののうち軽度認知症が4割を超えていたことや、発見者の約半数以上が家族等の捜索関係者以外であったことも注視すべき事例といえる。
こうしたことから、生存した状態で早期発見をするためにも、地域単位での捜索及びそのためのシステムづくりが肝要だといえるのだ。
▼外部リンク
桜美林大学老年学総合研究所
【この記事を読んだ方へのおすすめ記事】
- 認知症は予防できます!! –認知症「予防」のための3資格-
- 認知症予防医/広川慶裕医師の新刊「脳のスペックを最大化する食事」7/20発売
- 認知症予防医/広川慶裕医師の新刊「潜伏期間は20年。今なら間に合う 認知症は自分で防げる!」
- 広川慶裕医師の、認知症予防のことがよく分かる『認トレ®️ベーシック講座』開講!
- 知ると知らないじゃ大違い!民間介護保険って何?
- 酸化ストレスを減らすと認知症予防に!秘密はサプリメント
- ユッキー先生の認知症コラム第92回:あるべき姿の認知症ケア
- 認知症専門医による認知症疾患啓発イベントを開催
- ポイントは食生活にあった。認知機能維持に必要なのは・・・
- 認知症予防は40代から!摂ると差が出る栄養素とは。
- 山口先生のコラム「やさしい家族信託」第17回:Q&A 外出自粛で、認知機能の低下が心配。家族信託、遺言、後見、今できることが知りたい
- 【広川先生監修】5分で分かる認知機能チェック(無料)はこちら
- 認知症は予防できるの?
- 認知症の種類とその詳細はこちら








