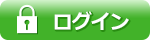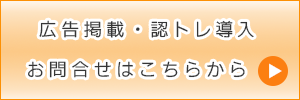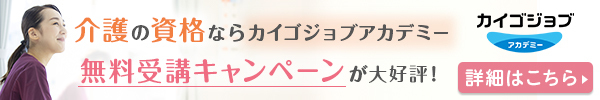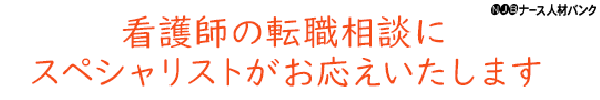【山村基毅さん連載コラム(第3回)】認知症と看護

取材を通して見つめなおした看護師という仕事
私の母親は、60歳で定年を迎えるまで看護師をしていた。地元の総合病院に長く勤めていたのだが、ひたすら忙しそうな姿しか記憶にない。月に何度か当直があり、その翌日には疲れ切って帰宅した。休日に遊びにも行かず、趣味らしき趣味ももたず、そんな人生の何が楽しいのか……などと若い頃の私は、不遜にも批判的な目を向けたものだった。
さて、『認知症とともに生きる』の舞台となった精神科病院ハートランドしぎさんでは、男性、女性、ベテランから若手に至るまで何人もの看護師に話を聞いた。親族を長期入院させている人たちから「ここの看護師さんは言葉遣いが優しい」「笑顔が暖かい」という評判を聞いていたため、実際の仕事ぶりを見せてもらいつつ、語ってもらったのだ。私にとっては、看護師という仕事、精神科医療における看護師の果たす役割を改めて見つめ直すこととなった。

確かな技術と確かな理念が患者を支える
認知症の方々の世話はさまざまな介護施設でも行なわれている。しかし、ここでは合併症をもった人が多いため、対応はさらに難しいものとなっていた。そもそも、患者は自身の症状(高血圧や糖尿病から発する合併症が多い)についてほとんど説明できない。
看護師が、彼らの顔色、動きを見て、症状の悪化や変化を読み取らねばならないのだ。ある看護師は「頭のてっぺんから足の先まで見ながら対応しています」と話していた。一部の患者がみせる介護抵抗というものがある。治療や介護に対して拒否反応を示し、激しく抵抗することがあるのだ。おむつ交換や車椅子への移動の際に暴れるだけでなく、自分の点滴を引き抜く、さらには同じ病室の他の患者の点滴まで引き抜こうとする場合もあるという。そうした行為を察知し、未然に防ぐのもまた、経験に裏打ちされた看護師の観察眼、そして対応なのである。
しかし、ベテラン看護師ならまだしも、20代と思しき看護師たちも、実に献身的に、なおかつ明るく看護に当たっていた。それについて看護部長の後藤文人さんから「自前の看護学校(ハートランドしぎさん看護学校)をもっていることもあるかしれませんね」といわれた。
准看護学校から数えると半世紀以上の歴史になる。卒業生も大勢ここで看護師をしている。長きにわたって培われてきた看護師としての姿勢が、後につづく者たちに伝わり、息づいているように思えた。
また、学生のときには、看護実習などでここの入院患者と触れ合う機会も多い。精神科病院に対して抱いていたイメージが、良くも悪くも変容していく。しかし、この場で「現実」に直面することで、自らの「理想」を測り直すことができるのだ。それでもなお「理想」を抱えられた者だけが、ここで看護師という仕事に就く。
「何の反応もなかった患者さんに、ちょっとした表情の変化があると嬉しいですよ」
「介護に疲れ果てていた家族の方が目に見えて元気になっていくと、やる気が出ます」
みな、眼を輝かせて語ってくれた。
今だからこそ気づく、母の仕事への誇り
そういえば、私の母が総合病院の産婦人科にいた際、本当に小さな身体の未熟児が生まれたのだという。その赤子が少しずつ少しずつ元気に育っていく様を、どこか誇らし気に話してくれたことがあった。
今なら、疲れた表情の裏にあった、母なりのささやかな矜持に気づいてあげられるのだ。
(画像はイメージです)
【主な著書】
▼関連記事
【山村基毅さん連載コラム(第1回)】鉄道事故の判決から考える認知症ケア
【山村基毅さん連載コラム(第2回)】保育園問題との対比から考える認知症介護離職
認知症のケアと介護
- 認知症予防医/広川慶裕医師の新刊「脳のスペックを最大化する食事」7/20発売
- 認知症予防医/広川慶裕医師の新刊「潜伏期間は20年。今なら間に合う 認知症は自分で防げる!」
- 広川慶裕医師の、認知症予防のことがよく分かる『認トレ®️ベーシック講座』開講!
- 知ると知らないじゃ大違い!民間介護保険って何?
- 酸化ストレスを減らすと認知症予防に!秘密はサプリメント
- ユッキー先生の認知症コラム第92回:あるべき姿の認知症ケア
- 認知症専門医による認知症疾患啓発イベントを開催
- ポイントは食生活にあった。認知機能維持に必要なのは・・・
- 認知症予防は40代から!摂ると差が出る栄養素とは。
- 山口先生のコラム「やさしい家族信託」第17回:Q&A 外出自粛で、認知機能の低下が心配。家族信託、遺言、後見、今できることが知りたい
- 【広川先生監修】5分で分かる認知機能チェック(無料)はこちら
- 認知症は予防できるの?
- 認知症の種類とその詳細はこちら