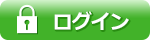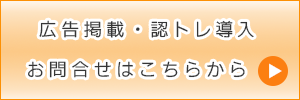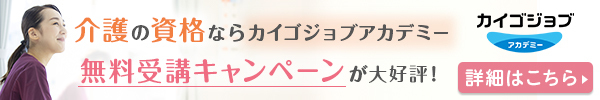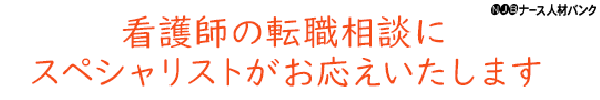第2回 認知症患者へ安心感を与えるコミュニケーションとは
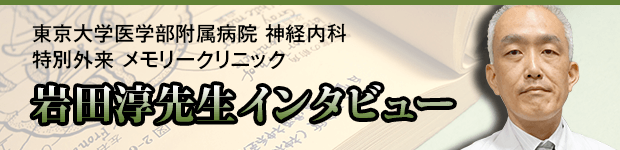
今回は東京大学医学部附属病院 神経内科 特別外来 メモリークリニックでアルツハイマー病(AD)やレビー小体病、前頭側頭葉型萎縮症等の疾患の診断、治療に当たっていらっしゃる岩田淳先生にインタビューさせていただきました。
岩田先生は認知症の診断・治療だけではなく、臨床研究も行っておりますので、認知症の研究も含めた幅広い内容をお伺いさせていただきました。全9回でお送りいたします。
岩田先生のインタビューを第1回から読む- 話し手
-
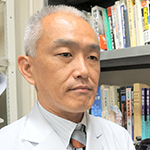 東京大学大学院医学系研究科神経内科学 講師岩田淳先生
東京大学大学院医学系研究科神経内科学 講師岩田淳先生
第2回 認知症患者へ安心感を与えるコミュニケーションとは
これまでしっかりしていた親、もしくは配偶者とのコミュニケーションが徐々にとれなくなってきてしまうこともある認知症。伝えたいことをどのように説明すればよいのか、どう接すればよいのか、家族は悩んでしまうこともあるでしょう。
ときには、それが家族にとっても認知症患者にとっても負担になってしまうこともあります。認知症患者に寄り添い、安心感を与えるコミュニケーションのポイントについてお聞きしました。
認知症患者には自覚がないケースもある
―― 認知症患者の方とコミュニケーションをとるうえで、本人に認知症の自覚があるかないかで対応の仕方も変わってくると思うのですが、認知症の方たちは、ご本人に認知症だという自覚はあるのでしょうか?
それは段階によります。軽症の方であれば、ご自分でも「ちょっと危ないな」と思われている方が多いと思います。進行してくると、自覚がなくなってきます。
いわゆる軽度認知障害であるとか、ごく軽症の認知症場合は、本人が悩んでいて、家族が気にしていないというケースが多いのですが、認知症になると逆になります。
初診で家族同伴の方に「どうしたのですか?」と尋ねた時に、「いえ、私は何ともありませんが、この人が行けと言ったので」という返答が返ってくる時は、その時点で既に認知症を強く疑う根拠になります。」
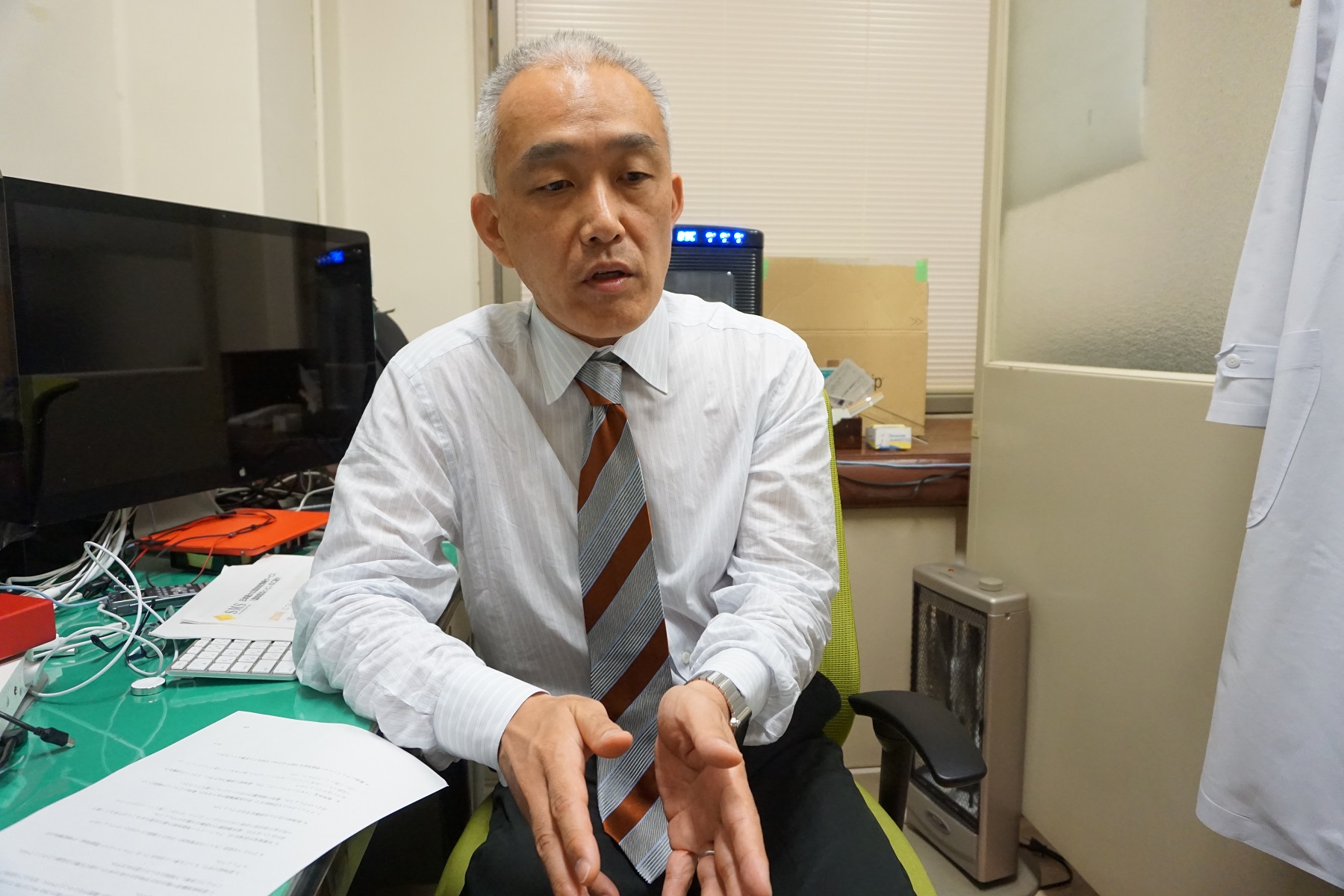
―― 患者さんご本人はしっかりしていると思っているということですね。先生の前ではしっかりしていても、ご自宅に戻られるとおかしいというようなことを昔聞いたことがありますが、そういう状態というのはありますか?
それはあるみたいですね。診察では「おうちではどうですか?」「今はしっかりされているように見えますけれども、ご自宅ではどうですか?」と、違いを訊くようにしています。するとご家族の方が「先生の前でだけ、しゃんとしています」という時もあります。
その場合は「ここだけでもしゃんとできて良かったですね」という言い方で返すようにしています。というのも、「家でもちゃんとしないと駄目だよ」なんていっても、患者さんはまず覚えていないですし、言質をとると、ご家族が「先生にちゃんとしないとだめって言われたでしょ」、といってご本人は「そんなこと聞いていない」などと言うことになって言い争いの原因になるからですね。
言い方にひと工夫、「重荷になっている」と感じさせないこと
―― 例えば、患者さんご本人に認知症の自覚がない場合、デイサービスなどに行くのを嫌がるケースなどもあると思いますが、このような場合はどういった対応をすればいいのでしょうか?
今まで行ったことのない、新しい場所に行かなければならないというのは、認知症の方にとっては恐怖そのものです。でも、そういう時に、「あなたが若い人の雇用を創出してあげているのだから、偉ぶって行ってあげて下さい」とお話しすると、受け入れてくださる患者さんが結構いらっしゃいます。
―― その言い方は素晴らしいですね。
認知症の方にとって、自分が誰かの重荷になっているとか、負担になっているという状況は、ものすごくプライドを傷つけるのです。そのプライドを逆に利用して、「あなたは人の為になっている」というと、喜んでいただけます。
―― それはケアの観点からも、本当に大事な視点ですね。
良い事に対して褒めちぎるのは大事だと思います。彼らは今までの人生の重荷を背負って生きてきている訳ですから。それまで、例えば社長さんだとか、社会的地位のあった方もいるだろうし、例えば主婦の方でも、今まで主婦業を何十年もやってきたという自負もあるでしょうから、そういうものが、いきなり誰かの世話になって、社会の重荷になってしまうというのは、耐え難い苦痛だと思います。その苦痛を感じさせないようにするということが、とても大事だと思います。その苦痛を感じさせないようにするということが、とても大事だと思います。
診察でも、楽しんでもらえることを大切に
―― 先生ご自身も患者さんに寄り添った対応をなさっておられますが、診療の中で工夫されて身につけられたものなのか、それとも他のところで学ばれたのでしょうか?
実は、私の父は神経内科医です。父をみていて色々と学んだ面もあるし、私の師匠である前々教授の萬年徹先生、前教授の金澤一郎先生、現教授の辻省次先生やローテーションでお世話になった慈恵医大の前教授の井上聖啓先生といった先生方というのは、『神経内科の病気には治らないものが多く、病気と共に暮らしていくことが必要となった場合に医師はどう接するか』という事をとても大事にして患者さんと接し、支えていく診療をすることをとても大切にされる先生方です。
患者さんに、治らないけれどもこの医者に診てもらってよかったと思って頂けるか、患者さんは亡くなってしまったけれども、ご家族があなたに診療してもらって本当によかったと言って下さるかということを最も大事にするような診療をしておられるので、その先生方の診察風景をみて勉強してきたことですかね。
―― 今は認知症の方にドライに接する医師が多いように思います。
大分昔と雰囲気は変わっていることは確かですね。ただ私は、今日は外来に行って、医者に診てもらって、薬が出たというだけで帰られるよりも、今日は何か一ついい話を聞いた、外来に行って楽しい気分になったと思ってもらえるといいなと思います。患者さんは楽しい気分は絶対に覚えているので、そういう気分で帰ってもらえば、少なくとも受診した意味はあるのではないでしょうか。
外来に続けて来てもらうということが最終的には大事なことですから、そのためには、楽しく外来に通っているという状況をつくらないといけないですね。また、認知症の診療には目の前にいる人の過去の出来事、現在の生活など幅広い事がらを知ることがとても大事です。雑談をこちらから持ちかければ、向こうからも、普通は医者には言いにくいなというような話を言い出せるような状況にはなります。
第3回「認知症が疑われるときのチェックテストと病院選びについて」に続く 岩田淳先生の他のインタビューを見る- 認知症予防医/広川慶裕医師の新刊「脳のスペックを最大化する食事」7/20発売
- 認知症予防医/広川慶裕医師の新刊「潜伏期間は20年。今なら間に合う 認知症は自分で防げる!」
- 広川慶裕医師の、認知症予防のことがよく分かる『認トレ®️ベーシック講座』開講!
- 知ると知らないじゃ大違い!民間介護保険って何?
- 酸化ストレスを減らすと認知症予防に!秘密はサプリメント
- ユッキー先生の認知症コラム第92回:あるべき姿の認知症ケア
- 認知症専門医による認知症疾患啓発イベントを開催
- ポイントは食生活にあった。認知機能維持に必要なのは・・・
- 認知症予防は40代から!摂ると差が出る栄養素とは。
- 山口先生のコラム「やさしい家族信託」第17回:Q&A 外出自粛で、認知機能の低下が心配。家族信託、遺言、後見、今できることが知りたい
- 【広川先生監修】5分で分かる認知機能チェック(無料)はこちら
- 認知症は予防できるの?
- 認知症の種類とその詳細はこちら